企業はなぜDXの内製化を目指すのか?理由と事例を紹介
- ブログ

近年、多くの企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組んでいます。DXとは、デジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセスを変革し、競争力を高める取り組みのことです。
AIやクラウド、IoTといった技術の進化により、業務の効率化や新たな価値の創出が可能になりました。
その中で注目されているのが「DXの内製化」です。
従来、ITシステムの開発や運用は外部のベンダーに委託するのが一般的でした。しかし、最近では社内にエンジニアやデジタル人材を育成し、自社でDXを推進する企業が増えています。
今回は、その理由を解説するとともに、成功事例を紹介します。
企業がDXを内製化する理由
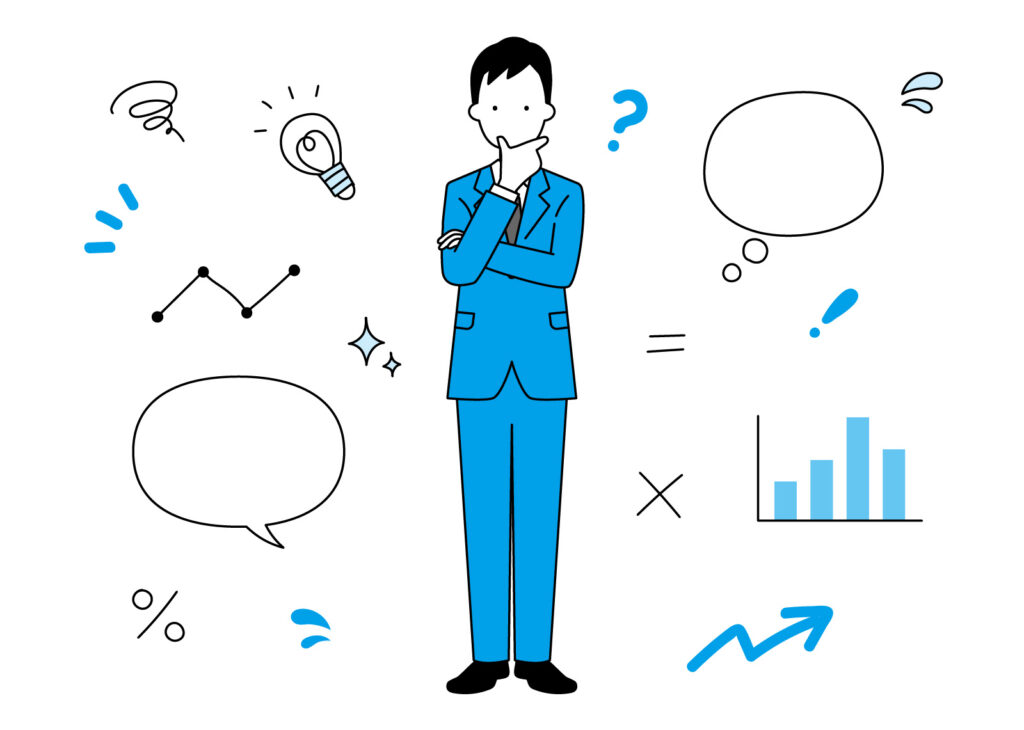
なぜ多くの企業がDX内製化を目指すのでしょうか?
その背景には、ビジネスとITの統合、データの活用、そして社内外の変化への対応能力が重要視されていること、オンライン化やテレワークが加速したことなど、DX推進とデジタル活用の必要性が高まったことが挙げられます。
より具体的な背景として、大きく以下の要因が挙げられます。
迅速な市場対応と競争力強化のため
今日のビジネス環境は、めまぐるしく変化しています。顧客のニーズや市場のトレンド、そして競合の動向も刻々と変化する中で、企業は迅速かつ柔軟に対応していくことが求められます。
DXを内製化することによって、システム開発やデータ分析を自社内で行ない、外部委託に比べて意思決定のスピードが向上し、市場の変化に迅速に対応できるようになります。
社内で内製化できる体制を構築することで、自社のニーズ・問題点を正しく把握したうえで、環境変化にも素早く対応していくことが可能になります。
DX推進にあたって変化に対する柔軟性が向上する点は大きなメリットと言えます。
コストを削減するため
DXを外部に委託する場合、開発費用やコンサルティング費用、保守費用など、コストが高額になるというリスクが発生しますが、内製化によってそのコストは削減できる可能性があります。
もちろん、内製化には初期投資や人材育成のコストが発生します。しかし、長期的な視点で見れば、外部委託よりもコストを抑えられる可能性があります。
社内のデジタル人材育成と競争力強化のため
DXを進めるには、デジタル技術を理解し、ビジネスと結びつける能力を持った人材が必要です。外部に頼るばかりでは社内にノウハウが蓄積されず、DXの推進力が弱まる可能性があります。
内製化を進めることで、社内にデジタル人材を育成し、企業の競争力を高めることができます。
内製化が進んでいる組織では、DXが共通言語として定着しやすく、従業員間のコミュニケーションエラーが起きにくくなるというメリットがあります。また、DXリテラシーが向上することで、業務課題の発見から解決策の提案まで、より本質的な改善アプローチを取ることが可能になります。単にシステムを導入するだけでなく、業務プロセス全体を見直し、最適化するという視点が組織内に広がることで、より効果的なDX推進が実現します。
セキュリティとデータ管理のため
DXの進展により、データが企業の重要な資産になっています。しかし、外部ベンダーにシステムを委託すると、どうしても機密情報や顧客データが外部に流出するというリスクを抱いてしまいます。
内製化することで、データ管理の主導権をそれぞれの企業内で握ることができ、セキュリティを強化することに繋がります。
外注依存のリスクを軽減するため
外部のITベンダーにシステム開発を委託すると、システムがブラックボックス化するリスクがあります。
システムの内容や仕組みがわからないと担当者が変更になった場合などに、システムの運用が難しくなることもありますが、DXの内製化により、システムへの理解が進むことで防げる可能性があります。
さらに長期化すると、外部のベンダーに依存してしまう「ベンダーロックイン」という状態に陥ってしまう恐れもあります。
システムのアップデートや新規開発を行うたびに外注コストが発生してしまい、長い目で見るとコストがかさむこともあります。内製化することで、こうしたリスクを軽減することが可能になります。
企業におけるDX内製化の成功事例
ここでは、異なる業種における具体的な成功事例を紹介します。ここでの事例では、ITベンダーへの依存を減らし、自社でデジタル技術を活用することで競争力を向上させており、DXの内製化が企業の競争力を高める鍵であることがわかります。
自動車業のソフトウェア開発の内製化
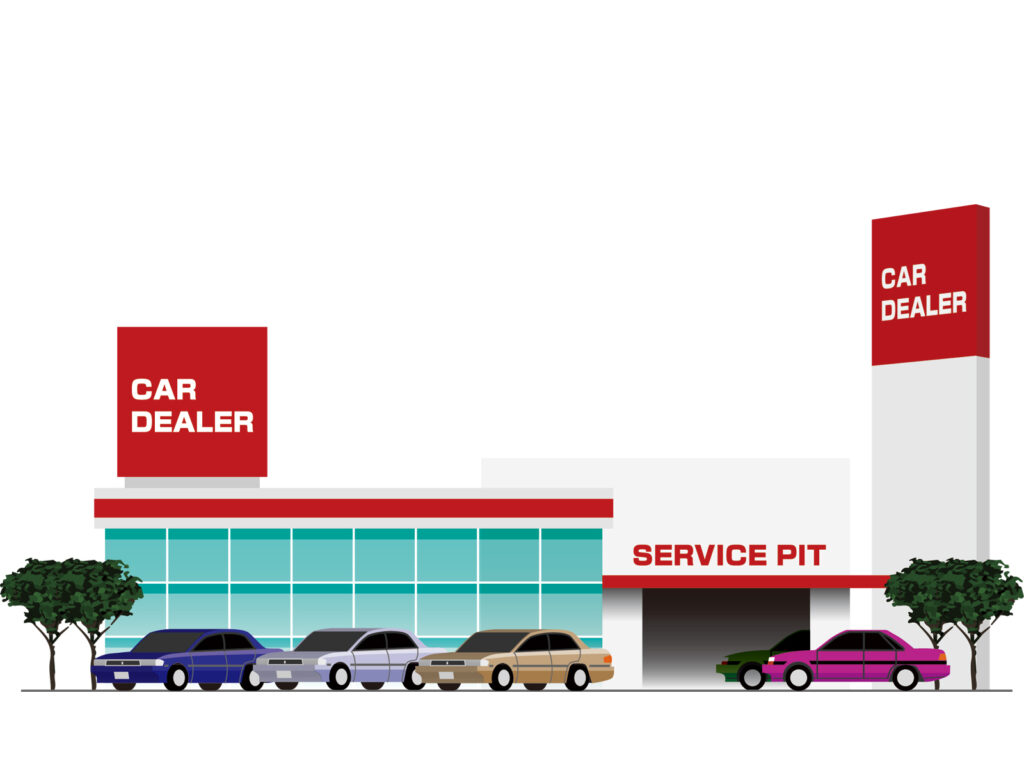
自動車製造業では、自動車産業のデジタルシフトに対応するため、ソフトウェア開発を内製化しています。
従来の自動車はハードウェアである車のパーツや部品を主に製造していました。
しかし、昨今ではEV(電気自動車)や自動運転技術の進化により、ソフトウェアの重要性が増しています。
その中で自動車製造メーカーでは、インターネットと連携する「コネクテッドカー」などの技術の強化のため、エンジニアの採用強化やリスキリング(再教育)を実施し、専門のソフトウェア開発チームを社内に設立。これにより、ソフトウェアの開発スピードを向上させ、市場の変化に迅速に対応できる体制を構築しています。
製造業での工場の無人稼働の実現

ある製造業の企業では、DX推進による生産性向上と業務省力化を実現しています。深刻な人口減少問題に直面し、従来の業務体制維持が困難になると予測したことから、工場の自動化を進め、少人数でも効率的に稼働できる体制を目指しました。
DX推進にあたり、コストパフォーマンスを重視し、機能の検証を徹底的に行った上で自社に最適なシステムを選定し導入しました。
その結果、システム導入により社外からでも工場の状態が確認できるようになり、工場の無人稼働を実現しました。このことで、生産状況の記録・追跡能力が向上したほか、従業員の負担軽減にもつながりました。
製造業でのデータ管理の属人化解消
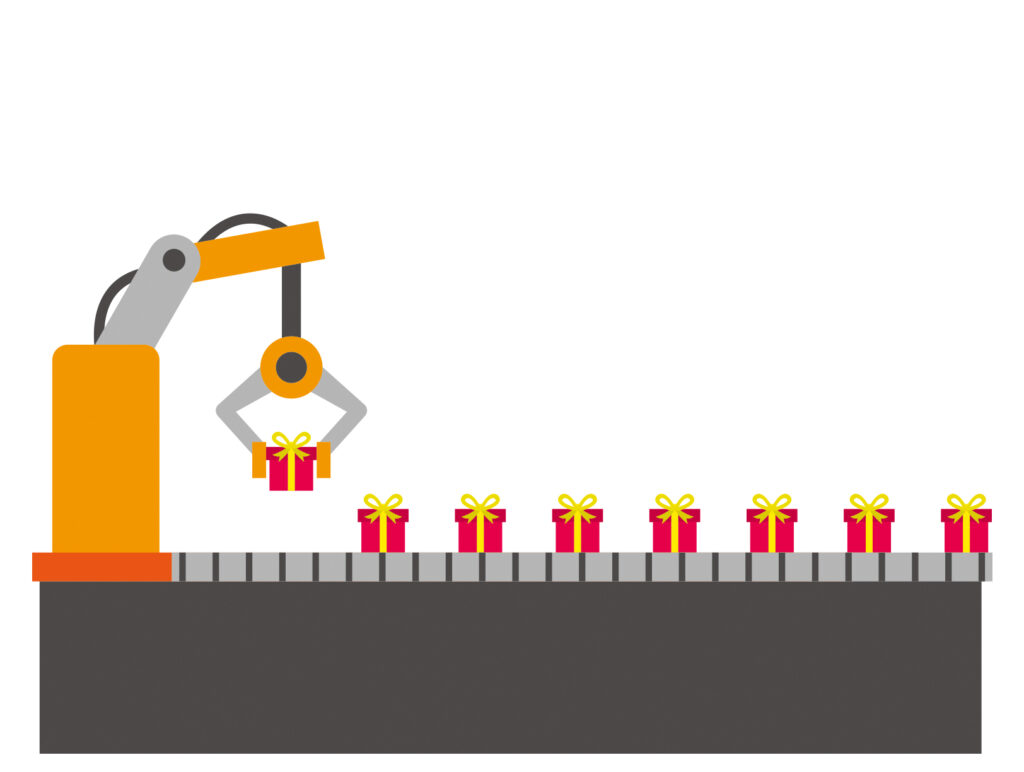
別の製造業では、特定の担当者に依存していた業務の属人化を解消し、データの可視化を実現することで、より効率的な生産管理体制を構築することに成功しました。
製造業では生産工程の細かなデータを収集・分析することで、品質向上やコスト削減、生産計画の最適化など多面的な効果が期待されています。
そのためこの事例では、製造業におけるDX内製化が単なる自動化だけでなく、ビジネスモデル全体の見直しにつながる可能性を示しています。
観光業でプログラミング未経験でのシステム開発

観光業の企業では、事業拡大の過程で、色々な会計ソフトとグループウェア、BIツールを連携させるようになっていました。
しかし、異なるシステム間の連携は複雑で、利用することに時間やコストがかかることが課題でした。
そこで、データ連携ツールを活用し、プログラミング未経験の担当者が自らシステム開発を行い、システム連携を実現しました。
エネルギー業界でのDX推進チームの設置
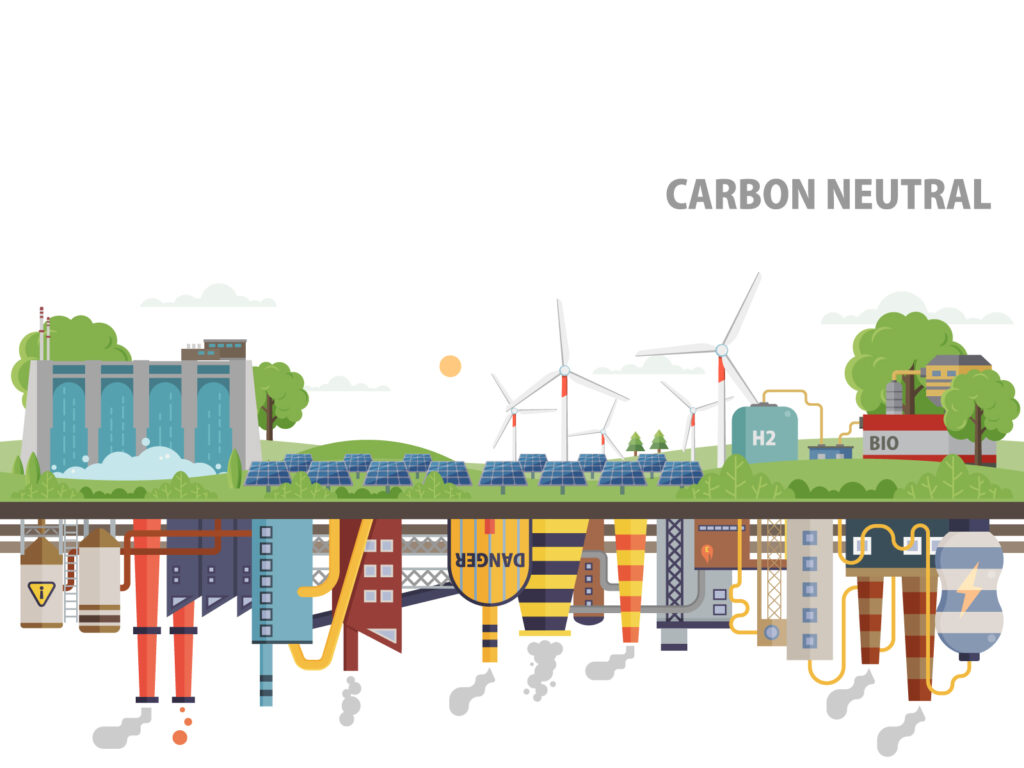
エネルギー事業を営むある企業では、システムの老朽化による労働力不足に対応するため、DX推進による労力削減を目的として社内にDX推進チームを設置し、DX推進戦略の策定を行ないました。そこでは月1回のDX勉強会の実施や社員のスキル習得のための教育の計画などが決定されました。
また、クラウドサービスの表計算ツールを活用して在庫や発注状況などを管理し、データの可視化を実現しています。この事例は、専門的なITスキルを持つ人材が限られている中小企業においても、既存のクラウドサービスを効果的に活用することで大きな成果を上げられることを示しています。
また、明確な目標設定と社内チームの設置により、組織的にDXを推進する体制を構築した点も成功の要因と言えるでしょう。
DX内製化のために必要なこと

DX内製化を成功させるためには、いくつかの重要な要素があります。同時に、内製化に伴う課題も理解し、適切に対処することが重要です。
経営層のコミットメントと全社的な取り組み
DX内製化の成功には、経営層の明確なビジョンとコミットメントが必要です。
DXはITの取り組みに収まるものではなく、企業全体の変革を目指す戦略であるため、経営層の推進力が重要となります。同時に、現場レベルでの理解と協力も不可欠であり、全社的な取り組みとして位置づけることが成功の鍵となります。
特に経営者自身がDXの重要性を十分に理解し、積極的に関与することで、限られたリソースの中でも効果的な推進が可能になります。
また、DXの目的や期待される効果を全社員に明確に伝え、共通認識を形成することも重要です。従業員がDXの必要性を理解し、自分たちの業務にどのような変化や改善をもたらすかを具体的にイメージできることで、変革への抵抗を軽減し、積極的な参加を促すことができます。
人材育成と技術力の強化
DX内製化の課題の一つは、必要な技術スキルを持つ人材の確保と育成です。特に中小企業では、専門的なIT人材の採用が難しい場合も多く、既存の社員のスキルアップが重要となります。
また、DXリテラシーがないまま業務の課題を発見し、業務プロセスを改善しようとしても、システムありきの解決策を考えてしまう可能性があります。全ての社員に一定レベルのDXリテラシーを身につけさせることで対策ができます。
そのために社内研修プログラムの整備や外部の教育リソースの活用、OJTでの実践的な学習機会の提供など、複合的なアプローチでDX人材の育成を進めることが効果的です。
コストパフォーマンスを高める施策
DX内製化を進める際には、コストパフォーマンスを高めるための戦略的な施策が大切です。DX推進のための費用が高くなりすぎないよう、機能の検証を行い、自社に最適なシステムを導入することが効果的です。
また、クラウドサービスの表計算ツールなど既存のサービスを活用することで、独自システム開発に比べて低コストでDXを推進することも可能です。短期的な投資の意味でのコストパフォーマンスだけでなく、長期的な視点での判断が重要となります。
段階的にDXを進める
中小企業のDXにおいては、大規模なプロジェクトを一度に実施するのではなく、小規模な実証実験から始めることが効果的です。段階的に取り組むことで、限られたリソースでも効果的にDXを進めることができます。
段階的なアプローチでは、リスクを最小化しながらもDXのメリットを確実に享受でき、初期の成功体験が組織内でDXへの理解と支持を広げる可能性も高まります。小さな成功を積み重ねることで、従業員のDXリテラシー向上にも貢献し、より高度なDX施策への取り組みを可能にするという好循環を生み出すことが期待できます。
まとめ

DX内製化は、企業の持続的な競争力を確保するための戦略的取り組みとなっています。特に中小企業においては、限られた経営資源の中で最大の効果を得るための重要なアプローチとして、その重要性は今後さらに高まるでしょう。
事例から見えてくるように、限られたリソースの中でも創意工夫により効果的なDX内製化が可能です。経営層のコミットメントや全社的な取り組み体制の構築、人材育成により、急速に変化する市場環境においても、DX内製化の能力を持つことで、企業の持続可能性と成長性を高めましょう。

